
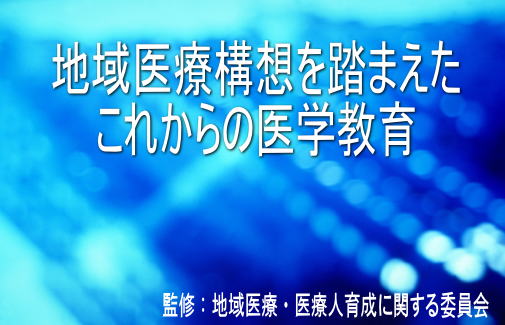 |
| *第41回* (R7.2.17 UP) | |
| 今回は東京科学大学での取り組みについてご紹介します。 | |
| 地域医療構想を踏まえたこれからの医学教育 | ||||||
|
||||||
|
【東京科学大学における地域枠学生の卒前教育】 東京科学大学(旧東京医科歯科大学)医学部は2025年度入学試験の時点で、茨城県、長野県、埼玉県の各県の枠5名の合計15名を定員として、地域枠の学生を受け入れている。この3県と連携する理由として、従来から、この3県には本学医学部との繋がりの深い関連病院が複数あり、多くの本学関係者が医師や管理者として勤務していることがあげられる。そのため、各県内の医療事情に精通しており、卒前教育、卒後教育、専門医研修の計画が立てやすい環境がある。 【地域枠医師の専門医と学位取得の取り組み】 卒後教育の特徴としては、県内勤務の義務年限の9年のうち3年以上を、本学の関連病院で勤務できるようなローテーションを組むことにより、その期間に専門医取得に必要な症例や技能を経験できるようにして、内科、外科、総合診療科などの専門医を取得できるよう工夫している。専門医取得のために、どうしても県外病院での研修が必要な場合は、義務年限終了が先延ばしにはなるが、県の規定で認められる期間内に限り、県外病院に勤務することもある。 こうした地域枠入学者に係るカリキュラムの企画、運営、評価及び改善のための活動を報告するための会議体として、地域特別枠対応委員会を設置し、各県関係者と本学とで年1~2回程度開催して、本学と各県との情報交換の場を設けて連携を強化している。本学のこうした地域枠の卒前・卒後教育の工夫が功を奏して、これまでの離脱者はごくわずかであり、義務年限終了後もその県の本学関連病院や地域中核病院などに定着して勤務し、その県の地域医療を支える医師を多数輩出している。 |
||||||