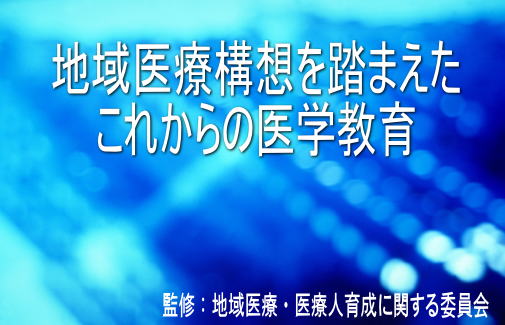|
徳島県における医師不足の現状と課題
徳島県は人口10万人あたりの医師数が336人と全国平均の262人を大きく上回り、全国1位である(厚生労働省 令和4年医師統計)。しかし、この数値が示す医療の充実は県全体には及んでおらず、地域ごとの医師の偏在が深刻な課題となっている。
第一の課題として、若手医師数の減少が挙げられる。特に35歳未満の若手医師の四国外への流出が進んでおり、徳島県の医師の高齢化が進行している。徳島県の医師の平均年齢は54歳であり、全国平均の50歳を上回る。若手医師の県外流出の背景や要因として、県外の大規模な医療機関では、指導医が豊富で教育カリキュラムが整備され、教育の質が高いというイメージが先行している可能性がある。しかし、人口当たりの若手医師数は東京等の大都市圏で多いため、大都市圏での研修がほんとうに充実しているのか根拠に乏しい。2004年に新医師研修制度の導入により初期臨床研修が必須化され、医師が研修先を自由に選択できるようになった。さらに専門分野で高度な知識と技能を習得し、専門医資格を取得することを目的に2018年に導入された新専門医制度では、日本専門医機構による専門研修プログラムから専門研修が、全国統一の枠組みに移行した。他県の病院の取り組みや研修の満足感はSNSを通じて学生・研修医間で迅速に共有されている。地方においてもしっかりとした初期研修、専門研修ができることを学生・若手医師に示すことが重要である。また都市圏に比べて娯楽や生活の利便性で劣ると感じる県外出身学生が一定数おり、県内出身学生でも地元を離れ、新しい環境で経験を積むことで個人として成長したいという志向等による地理的・生活環境の要因もあるかもしれない。一時的に地元や母校を離れても、いつかは帰ってきて徳島の医療に貢献したいという意識を卒前早期から地域医療に触れることで育成する必要がある。さらに地域医療を担う医師の不足や労働環境の課題が報じられている中、将来地域医療を担うことに不安を感じているかもしれない。働き方改革を進める上で、若手医師に過度な不安を与えないような情報発信が必要である。
第二の課題として、県内における医師、診療科の偏在が挙げられる。大学病院や基幹となる病院が多い徳島市や鳴門市を含む東部医療圏には医師の75%以上が集中し、特に徳島市には全体の52%が偏在している。一方で、南部医療圏には400人、西部医療圏には160人と、山間部や県南部での医師不足が顕著である。この偏在により、地域によっては医療を受ける機会が制約される状況が続いている。また、産科や小児科、救急医療分野では診療科偏在が存在し、医療ニーズに十分対応できていない。
このように新医師臨床研修制度に続く新専門医制度の中で、四国全体で若手医師の四国外流出、医師高齢化、医師・診療科偏在が顕著であり、単純な人口当たりの医師数だけでは地域医療の医師不足を論じると県内医療の崩壊につながる可能性があり、徳島県地域医療構想の中で包括的に対応する取り組みが求められる。
徳島大学医学部の取り組み
徳島大学医学部は地域医療構想を踏まえ、地域医療に貢献できる医師の育成に注力している。2007年には徳島県の寄附講座として大学院医歯薬学研究部に「地域医療学分野」を開設し、地域における教育・研究を本格化させた。医学科4,5年生には県立海部病院を中心とした診療参加型実習Iを必修科目として導入し、学生が1週間にわたり地域医療機関や介護施設で実地研修を行い、地域医療の課題を体感する機会を提供している。また、離島診療所の見学を通じて、僻地医療への理解を深める実習内容となっている。
診療参加型実習IIでは、5年生から6年生にかけて学生が3~4週間の地域病院実習を行い、実践的に診療に参加することで深い学びを得る機会を提供している。これらの経験を通じて、学生は地域に愛着を持ち、地域医療の重要性を実感し、地域視点を持った将来のキャリア形成に活かしている。現在、医学科3年生で社会医学実習が初めての地域医療実習となっているが、コロナ禍で開始が遅れていたさらなる低学年で地域医療を体験するプログラムの導入を模索している。医学生が地域医療に触れる機会を増やすことで、若手医師が地方医療に関心を持ち、従事する動機を高めることが期待される。
2010年には「地域医療学分野」から「総合診療医学分野」に改称され、県立海部病院と連携し、教員増員により、診療支援・現場教育をさらに充実させ、地域医療の再生と総合診療医の育成に取り組んでいる。また、県南の阿南医療センターを中心とする実践地域医療・医化学分野や愛媛県の四国中央病院を中心とする地域総合医療学分野・地域医療人材育成分野などの寄附講座との連携により、包括的な診療参加型実習を展開している。
2022年の医学教育モデル・コア・カリキュラムでは、患者を総合的に見る能力(Generalism)の養成がさらに重要化され、2023年12月には「地域・家庭医療学分野」が大学院医歯薬学研究部に新設された。この分野の開設により、上記の寄附講座と一体となり、卒前から卒後までのシームレスな地域住民の健康促進を実践する医療人の育成を実践する教育体制が整備された。
また、徳島県医師修学資金貸与制度による地域特別枠制度を通じて地域医療機関で勤務する医師を育成している。卒前から卒後までシームレスに徳島県地域医療支援センターとの連携により、「総合診療力育成事業(徳島GMラウンド)」などの研修会の開催やなどの教育カンファレンスの実施などにより、医学生や若手医師の総合診療能力の向上を目的とした教育プログラム提供等を通じ地域医療の担い手となる医師の育成を進めている。
さらに徳島県は、県内の医療機関で臨床研修や専門研修を行う県外出身の医師に対して、「一時金支援制度」を設けている。県内の臨床研修プログラムで初期臨床研修を行う場合、100万円の支援金が支給され、引き続き県内の専門研修プログラムで研修を行う場合には、追加で200万円の支援金が支給される。これらの制度等を有効に利用して、徳島県内の若手医師の絶対数を増加させる必要がある。
医師の偏在解消
自治体間で医師の適切な配置を調整し、医療資源の公平な配分を目指す必要がある。徳島大学は、徳島県地域医療支援センター、徳島大学病院キャリア形成支援センター、卒後臨床研修センターなどと連携し、専門研修を通じた医師のキャリア形成を支援することで医師の偏在解消に取り組んでいる。
医療インフラの強化
徳島県では、5G技術やICTを活用した遠隔医療の導入や、地域診療所のネットワーク化により、医療の質とアクセスの向上を本格化させている。診療においても今後、徳島大学病院や県立中央病院と地域医療機関を密接に結ぶ診療支援体制をさらに拡充する方針である。
今後の展望
徳島大学医学部は、地域医療の課題解決に寄与するだけでなく、医師としての使命感と倫理観を備えた人材の育成を進めている。今後も徳島県と連携し、卒前から卒後に至るシームレスな医学教育を通じて、地域に根付く医師の育成を推進する必要がある。
|